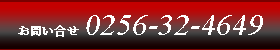今年こそはいい夢を、夢で茄子に…「一富士、二鷹、三茄子」
「一富士、二鷹、三茄子」とは、昔からのことわざで、お正月の夢に見るものの中で、おめでたいものの順番を指す言葉です。これらの夢を見ると大変縁起が良いと言われてきました。
富士山は日本最高峰の霊山です。また、鷹は鳶と共に鳥の王者です。おめでたいものの象徴としてはふさわしいものですが、茄子はなぜでしょう。
三つの説が挙げられています。
1.駿河国(静岡県中央部)の名物を順にあげた。
2.徳川家康が駿河国の高いものを順にあげた。
茄子は初物の値段の高さ。
3.富士山は高くて大きく、鷹はつかみ取る。
茄子は「成す」に通じて縁起が良い。
名物については、他の地域でも栽培されていたのではないのでしょうか?
初物については、江戸時代には油紙を障子で囲って促成栽培をしていたので、茄子の初物は非常に値段が高かったと言われています。
茄子はインドが産地で、奈良時代より前に日本に渡来、日本の高温多湿の気候に適していました。そして全国に広がって栽培され、各地に土着して品種ができました。
小型、瓜型、長なすと種類も多く、日本では大昔から冬は大根、夏は茄子と、この二つの野菜が大切な食料でした。
大切なものは必ずしも尊敬されずあざけることわざ「ぼけなす」「おたんこなす」に使われたり、また「秋茄子は嫁に食わすな」「瓜の蔓に茄子はならぬ」「親の意見と茄子の花は千に一つも徒(あだ)はない」など、ことわざの中でも多く出てきますし、良いことわざにも茄子は使われています。
有力な説としては、茄子はおしべとめしべを持つ両全花なので、このことわざができたのではないでしょうか。
実りやすい大願成就の意味を持っているからだと思います。
夢については朝日が昇る、月が山から昇るなども吉夢とされています。
来年こそはいい夢を。夢で茄子に会いましょう。
このコーナーは、若月郁子(わかつき・いくこ)が担当しました。